| 咳嗽・喀痰の診療 ガイドライン |
2025 |  |
急性咳嗽と遷延性・慢性咳嗽
なぜ咳がでるのか
・咳は、気道内に貯留した分泌物や吸い込まれた異物を気道外に排除するための生体防御反応です
咳の分類と原因疾患
| ・ | 咳は痰の有無により乾性咳嗽と湿性咳嗽とに分類される |
| ・ | 咳は持続期間により3週間未満の急性咳嗽、3週間以上8週間未満の遷延性咳嗽、8週間以上の慢性咳嗽に分類する |
| ・ | 喘息、咳喘息は慢性咳嗽の頻度の高い原因疾患 |
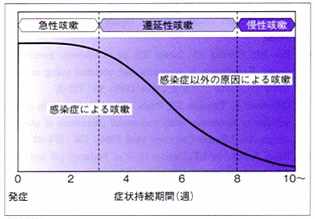
急性咳嗽の多くはウイルス性の普通感冒を中心とする気道の感染症です。持続期間が長くなるにつれ感染症の頻度は低下し、遷延性咳嗽では、感染後咳嗽がもっとも多い。慢性咳嗽においては、感染症そのものが原因となることはまれです
図. 症状持続期間と原因疾患の比率
| フローチャート① | 成人急性咳嗽への対応 |


| フローチャート② | 成人遷延性・慢性咳嗽への対応 |


| ※1,2: | 肺結核などの呼吸器感染症、肺癌などの悪性疾患、喘息、COPD、喫煙による慢性気管支炎、気管支拡張症、薬剤性肺障害、心不全など |
| ※3: | 上気道咳嗽症候群(UACS)については耳鼻咽喉科との連携を考慮する。鼻副鼻腔炎には、好中球性炎症を主体とする従来型の鼻副鼻腔炎と、抗酸球性炎症を主体とする抗酸球性副鼻腔炎がある。抗酸球性副鼻腔炎は喘息の合併が多い。診断はJESRECスコアで疑い、耳鼻咽喉科専門医に診断を依頼する |
| ※4: | 喀痰塗抹・培養(一般細菌、抗酸菌)、細胞診、細胞分画や胸部CT検査、副鼻腔X線またはCT検査を施行する |
| ※5: | まずエリスロマイシン(EM)を使用し(400~600mg/日)、有効性が得られない場合や副作用が出現した場合は、他のマクロライド系抗菌薬を考慮する |
(日本呼吸器学会 咳嗽・喀痰の診療ガイドライン2025より抜粋、一部改変)
